公開日 2014年01月21日
目的の史跡・文化財をクリックしてください。詳細情報が得られます。
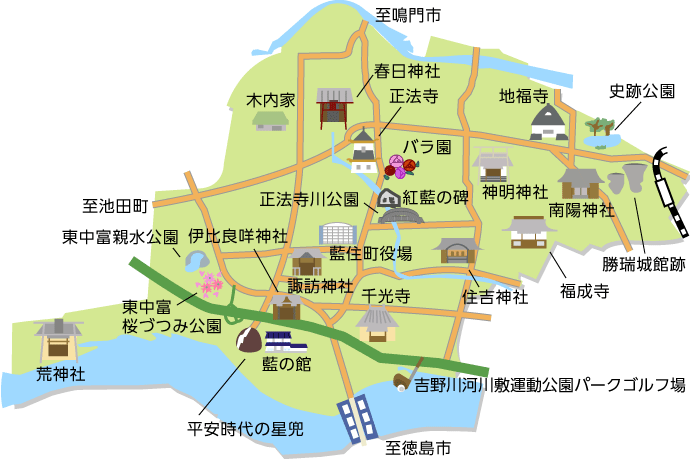
観光施設
歴史館「藍の館」

藍住町は、町名にある「藍」の一文字が示すとおり、江戸時代から明治30 年代まで阿波藍の一大産地として広く知られていました。藍の館は、昭和62 年に大藍商であった奥村武夫氏から旧屋敷や文書などを寄贈されたのを機に、全国でも珍しい藍の専門資料館として平成元年8月に開館しました。現在、藍などの天然染料が見直されている中で、藍染体験や民俗資料の見学ができ、地元はもちろん全国的にも人気が高い施設です。
(所在 徳島県板野郡藍住町徳命字前須西172、171-1)
バラ園

園内には、約270 種類、1,000 株のバラが植えられおり、シーズンになるとバラ園は色鮮やかな花々と豊潤な香りに包まれます。見ごろに合わせ、春(5 月上中旬)と秋(10 月下旬)の年2回、バラまつりが開催されます。春と秋それぞれに特徴があり、春は花数が多く様々な品種を見比べることができ、秋は春に比べて花数は少ないものの、香りが豊かで色鮮やかなバラが咲きます。また、園内にはバラのアーチがあり、バラを見上げての散策は幻想的です。
(所在 徳島県板野郡藍住町矢上字原263-88)
史跡公園


公園
正法寺川公園

平成7 年1 月に完成した「みどり橋」(一般公募により名称を決定)は、全長が60 メートルと西日本屈指の木造アーチ橋として親しまれており、平成8 年には「手づくり郷土賞」を受賞しています。
東中富桜づつみ公園

平成14 年に完成。旧吉野川に面した風光明美な公園です。公園内には石造りの水路や滝のほか、わんぱく広場や多目的広場が整備されています。春にはその名のとおり美しい桜を見ることができます。
東中富親水公園

平成5 年9 月に正法寺川浄化事業の一環として完成した公園。本公園も平成6 年に「手づくり郷土賞」を受賞しています。休日にはイベントや憩いの場として利用されています。また、この公園は浄化引水ポンプ設備を備えており、人工の滝を見ることができます。
吉野川河川敷運動公園

吉野川河川敷に整備された公園。パークゴルフのほか、サッカーなどの屋外スポーツを楽しむことができます。
歴史・文化
地福寺(ぽっくり地蔵)

石碑には「文治年間景徳上人の創設、正保年間玄賀上人一人の童子に導かれ、大往生地蔵尊を拝し、当地の永遠の繁栄と住民の息災、延命、大往生を誓願し、景徳山保久利院地福寺を中興。」と記されています。
南陽神社

細川弥九朗澄賢公によりこの地に祀られ、村民の氏神日枝神社として尊崇されていました。昭和二十七年に馬木に鎮座されていた八坂神社、天神社と合併し、その後昭和三十三年に東勝地に鎮座されていた勝瑞神社と合併しました。なお、この地の辺りを「南陽ヶ丘」ともいい、この地名にちなんで昭和三十七年に南陽神社と改称しました。
神明神社

神明神社は伊勢神宮の分神だとされ、神明神社を参拝すれば伊勢神宮に参詣したことになるといわれています。
福成寺

福成寺は中世に建立された古刹で、住吉神社の別当寺でした。境内には住吉城主の赤松則房の供養塔と伝えられる大五輪も置かれています。また、ここには町の有形文化財に指定されている地蔵菩薩像が安置されています。この尊像は凝灰石を素材としたもので、中世の石仏として貴重なものです。
住吉神社

当社は住吉四社神社といって、神功皇后・素盞鳴命・中筒男命・底筒男命の四柱を祭神とし、本殿は板葺の四棟のものが並んでいるという珍しい構造になっています。山田家文書によれば、源平合戦のとき源義経が戦勝祈願をしたことが記されています。また、戦国大名三好義賢が幼少の時神職を勤めたことがある由緒ある神社です。
春日神社

この付近は七世紀中頃まで皇室領の春日部屯倉が置かれていたところで、境内には県指定の「矢上の大樟」があります。
【矢上の大樟】
昭和31年に県の天然記念物に指定されている樹齢2000年ともいわれる樟の木。春日神社の鳥居をくぐって拝殿横を北に行った所にあります。矢上の地は、6~7世紀に皇室の直轄地である春日部の屯倉が置かれていた遺跡で、春日神社はそのころから存在していたとつたえられています。境内の大樟は、藩政期の「阿波名所図会」にも紹介されていて、三好郡の加茂の大樟とともに、阿波を代表する名木です。樹幹は、もと幹囲が17.8メートル、地上3メートルから大きく4つに分岐し、樹高は25メートルで下部には木肌に塊状のこぶが一面にみられます。この地の歴史を見守ってきた大樟です。
正法寺

正法寺中興の敬台院は於虎の方といわれ、徳島藩初代藩主蜂須賀至鎮正室、徳川家康の養女で、わずか九歳のとき十五歳の至鎮に嫁したのです。大阪の陣後に住吉藩が廃され、一万石の置塩領は敬台院化粧領に、その中心地にあった正法寺を再建、法華宗に改宗しました。その後藩の手厚い保護をうけ、その本堂は、いまも見事な天井絵をはじめ、すばらしい壮厳美が見られます。
紅藍の碑

昔から日本の二大染料として美しい色を生み出してきた藍と紅。阿波藍の里・藍住と最上紅花の里・河北町はともにこの伝統を守るために交流をはじめ友好都市の締結をしました。藍住町の藍の文化は紅花という伴侶を得て、さらに深みを増しそして豊かなものになっていくのです。
千光寺

昭和59年、町の天然記念物に指定された臥竜梅が有名なお寺です。初代徳島藩主蜂須賀至鎮(義伝公)が、こよなく愛したという千光寺の臥竜梅は、安政5年(1858)の記録には高さ8尺、幅3間半、長さ16間とあります。「阿波志」によると「千光寺は梅の坊と称し、臥竜1株あり」と記されています。当時の梅樹が枯れた跡に、八重梅が植えられ、見事な臥竜梅に育ち今日に至っています。梅の見頃は、2月中旬から、3月です。
伊比良咩神社

伊比良咩神社は延喜式外大社として高い格式を誇って東中富に鎮座していたといわれています。その後に現地に遷座したがその年代は不詳です。近世中期に改築された本殿・拝殿はケヤキを主材とした建築で、当地が阿波藍生産と全国市場への進出で繁栄していたことがうかがえます。また、200m東にあるお旅所の緑泥片岩の鳥居も珍しいものです。
平安時代の星兜

小塚出土の国産最古の星兜で、平安時代初期のものとされています。昭和59年に町の有形文化財に指定されています。星兜の星とは、兜の鉄板を留めている鋲の頭が表面にでており、この鋲の部分を星と呼びます。
